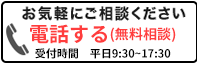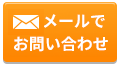「相続」って何?初めてでもわかる基礎知識を徹底解説
「相続」って何?家族の笑顔を守るために知っておきたい基本のき
「相続」と聞くと、どこか遠い世界の話のように感じたり、
「うちはお金持ちじゃないから関係ない」と思ったりするかもしれません。
しかし、実は相続はすべての人に訪れるライフイベントです。
いつか必ず向き合うこのテーマを、知識不足のために「争族」にしてしまわないよう、
基本的なことを一緒に学んでいきましょう。
相続とは、あなたの「想い」と「責任」のバトンタッチ
相続とは、あなたの大切なご家族(被相続人)が亡くなったとき、
その方が持っていた財産上のすべての権利と義務を、残された家族(相続人)が受け継ぐことです。
このとき重要なのは、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、
ローンや借金などのマイナスの財産も、すべてセットで引き継ぐ、という点です。
「財産」というと良いものだけをイメージしがちですが、負債の引き継ぎという責任も含まれていることを、最初に理解しておく必要があります。
期限との戦い!手続きの「3つのタイムリミット」
相続は、被相続人が亡くなった瞬間に始まりますが、遺族はいくつかの手続きを時間との勝負で進めなければなりません。
特に重要な、見落としてはいけない3つの期限を押さえておきましょう。
◆相続放棄の期限(3ヶ月)
もし、亡くなった方に借金が多いことが判明した場合、「相続放棄」という選択肢があります。
これはプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないという意思表示です。
期限は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内。
この期間を過ぎると、借金まで背負うことになる可能性があるため、故人の財産状況はすぐに確認しなければなりません。
◆所得税の準確定申告(4ヶ月)
亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わって確定申告を行います。
期限は死亡から4ヶ月以内です。
◆相続税の申告・納付(10ヶ月)
相続財産の総額が、法律で定められた基礎控除額を超える場合、死亡から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要です。
期限を過ぎると、余計な税金(ペナルティ)がかかるので注意が必要です。
誰が相続人になる?法定相続人のルール
誰が、どれくらいの割合で財産を受け継ぐ権利があるのかは、法律で厳格に決められています。
これを「法定相続人」と「法定相続分」と言います。
まず、配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。
そして、それ以外の親族は以下の順位で優先されます。
第1順位: 亡くなった人の子ども(孫なども含む)
第2順位: 第1順位がいない場合、亡くなった人の父母や祖父母(直系尊属)
第3順位: 第1・第2順位がいない場合、亡くなった人の兄弟姉妹
このルールは、遺言書がない場合に適用されます。
もし有効な遺言書が残されていれば、原則として遺言書の内容が法定相続のルールよりも優先されることになります。
「争族」を避けるために、今からできること
相続を巡るトラブルは、家族関係を修復不可能にしてしまうことがあります。
大切な家族を悲しませないために、ぜひ元気なうちから準備を始めましょう。
遺言書で意思を明確に: 財産の分け方を明確にする「遺言書」は、家族の対立を防ぐ最高の予防策です。
特に不動産など、分けにくい財産がある場合は必須と言えます。
財産のリストアップ: どこにどんな財産(負債)があるのかを一覧にした「財産目録」を作っておき、家族と情報を共有しましょう。
財産がわからなければ、手続きもスムーズに進みません。
相続は手続きではなく、家族の未来に関わることです。
基本を知り、一歩ずつ準備を進めることが、大切な人たちの笑顔を守ることにつながるのです。
****************************************
このコラムを読んで、少しでも相続に興味を持っていただけると幸いです。